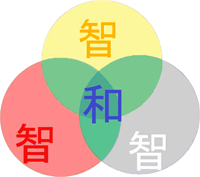私はその時まで、彼が精神的に病気だったことを知らなかった。
彼女は彼の病気について、話し始めた。
彼女は FAS と FAE という病名を言った。 初めて聞く用語だったので、私はそれが何を意味するのか分からなかった。 彼女は本棚の中から医学書を出してきて、それらの症状を私に読み聞かせた。
彼は医者から、 FAS だと診断された。 FAS は、日本ではまだまだ認知度が低く、関連情報の量も少ない。日本やアメリカ国内では患者数があまり多くないから、知られていないのだと彼女は言った。 「ネイティブ・アメリカンの間で、特に多い病気なの」と。
FAS とは Fetal Alcohol Syndrome の略で、「胎児性アルコール症候群」(「胎児アルコール症候群」または「胎児アルコール症」とも呼ばれている。 妊娠中の母親が多量のアルコールを摂取すると、胎盤を通じて胎児の体内にアルコールが直接入り込む。 通常、胎盤はあらゆる毒素を除去するのだが、アルコールだけはろ過されずに直接入り込んでしまう。
そのような胎児は、誕生する前からアルコールに浸されてしまい、先天的な障害を持って生まれてくる。
FAS の症状としては以下のようなものが挙げられる。
1)知能指数の低さ。学習能力に欠けている。→ 彼は文字の読み書きができない。
2)視覚・聴覚・記憶力の障害 → 彼はよく同じ話をする。記憶が定かではない。
3)行動障害 物事の善悪の判断がつかない
彼の母親は重度のアルコール依存症だった。 彼を身籠った時も、母親はアルコール摂取を止めなかった。 そうして 彼は生まれつき、アルコールの被害を受けていた。
彼自身も、まだほんの子供だった時からアルコールにおぼれ始めた。 彼の両親は仕事をせず、政府の援助金やフードスタンプを与えられていた。 彼の両親はそれらの食料や援助金を、すべてアルコールにつぎ込んだ。 そんな風に彼は、幼い頃からアルコールが手の届く所にあった。
彼は10代の初めから、既にアルコール依存症になっていた。 アルコール依存症になると、アルコールが無くなる事が何よりも怖くなる。 そしてアルコールの役割を果たしてくれるものなら、何でも口に入れるようになる。
マウスウォッシュやヘアスプレー、歯磨き粉などには、アルコールが含まれている。 これらを水で溶かして飲むようになる。 想像しただけでも吐き気がしてくるが、実際アル中の人々は離脱症状の苦しさから逃れるために、そうやって常にアルコールを体内に補給し続ける。
これを防止するため、保留地内のいくつかの店では、マウスウォッシュやヘアスプレーなどは店の奥にしまいこんでいて、本当にこれらの商品が必要な人だけに売るということをしている。
私は彼がアルコールを飲んでいる姿を、一度も見た事がなかった。
彼は何度もアルコール更正施設に入って、アルコールを体内から抜くという訓練を行っていたのだそうだ。それに、セレモニーを何度も受けながら、スピリットの助けを借りているからなのだそうだ。
彼女は自分の給料をほとんどすべて、彼の医療費やセレモニー費用に注ぎ込んできた。 そんなことが何年も続いているらしい。
「あなたは本当に彼のことを愛しているのね?」 と私が言うと、彼女はそれを否定した。
「怖いのよ。怖いから離れられないの。あの人は恐ろしい人だから……」
彼女は何度も彼の元を離れようと試みたらしい。 けれども、彼女がどこに行こうとも、彼は必ず彼女を見つけ出し、死ぬほど暴行を加える。 顔の形が変わるほど殴られた後、瀕死の状態の彼女を見て、彼は泣きじゃくりながら彼女に懇願するのだそうだ。 「お願いだから、僕を見捨てないで…」
そんなことが過去に何度かあった。 彼女は体が回復するまで2-3ヶ月入院した。 一度など、彼女に新しい恋人が出来て、駆け落ちのような形で逃げたのだが、彼は2人が一緒にいる所を見つけ出し、彼女の目の前で相手の男性を半殺しにした。
その後、彼はしらふに戻ったときに、罪悪感に苛まれて自分で自分の胸を銃で撃った。 弾は貫通したはずなのに、彼の体は数日で回復したのだそうだ。
そんなことがあったので、彼女は彼から一生逃げられないと悟り、人生をあきらめているのだと言った。
*********
私は今、起こった事を淡々と書き記しているが、実際には穏やかに話していた訳ではない。
彼女は混乱していて、私にすがりついて 「出て行かないで欲しい」 と懇願したり、「彼をその気にさせたのなら、責任を取って彼の面倒を見るべきだ」 とおどしたりした。 怒ったり泣いたり、威嚇したり懇願したり・・・。 そんな彼女の様子を見ていて、私自身も混乱していた。 何が本当なのか分からなかった。
何時間経ったのだろう?
私の中から理性がなくなりかけてきた。 もうここを離れることは出来ないんじゃないかと弱気になった瞬間、ナバホ父の声が胸に響いた。「必ず戻って来い。君ならできる」
その言葉で、はっと我に返り、私は声を絞り出して彼女に言うことができた。
「これ以上あなたの話を聞いていたくない。 どうかこのまま、私を出て行かせて欲しい」
私は荷物をスーツケースの中に投げ入れて、逃げるように彼らの敷地を去った。
私はなんて馬鹿だったんだ。 冷静になれば見えていたことすら、見えなくなっていた。