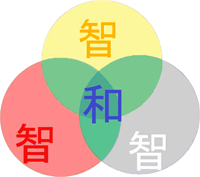私が子供の頃、家族メンバーに雄のシェルティ(シェットランドシープドッグ、ミニコリーとも呼ばれる)がいた。きれいな顔立ちをした、性格の優しい犬だった。私にとっては弟のような存在だった。 弟が11歳になったある日、私は夢をみた。弟が死ぬ夢だった。現実なのかと思うほど、はっきりとした夢だった。夢の中で私は泣いた。目が覚めて意識が現実に戻ってからも、涙が止まらない。 一階にいる弟の元に走って行って、弟を抱きしめた。弟の体は温かくて、私はほっとした。単なる夢だと思いたかった。けれど心のどこかで、それが予知夢だと分かっていた。 それから何日かが過ぎた。その日は日曜で、私はアルバイトに出掛けていた。昼過ぎになって、バイト先で館内放送が流れた。私の名前が呼ばれていた。 受付まで走っているときに、弟が逝ったことを母が知らせてきたのだと直感した。 走りながら、既に涙がこぼれ始めいていた。 受付の男性は電話を私に手渡した。案の定、母からの電話だった。受話器の向こうから母のすすり泣きが聞こえる。しばらく無言のまま、私は受話器を握り締めていた。 それから母は、搾り出すような小さな声で言った。 「もう動かないのよ」 私はその場で泣き崩れた。 私が家に着く頃には、父も仕事から戻ってくれていた。兄はその時東京に居たので帰って来られなかった。両親と私はしばらく弟の体をさすった。弟の体は冷たくて固かった。 まるで時が止まったみたいに静かだった。誰も何も言わず、ただ弟のそばに座っていた。 翌日、私達3人は弟を動物用の火葬場に連れて行き、お別れをした。そうして弟の体は、骨と灰になった。 葬儀から戻る車の中で、父はこんなことを言った。「この世の命あるものは全て例外なく、死を迎える宿命なんだ。時間は誰にも止められない。だから命ある限り、精一杯悔いの残らないように生きなきゃいけない。」 「悔いの無いように」の部分が引っかかった。私は弟にいつも誠実に接していただろうか? していなかった。都合の良い時だけ可愛がって、世話はほとんど母にまかせっきりだった。それなのに弟は私を癒してくれた。弟の存在は家族みんなを癒してくれていた。 私の愛する弟、誠実でなくてごめんなさい。たくさん思い出をありがとう。私の家族になってくれてありがとう。
Category Archives: japanese
「サバイバルトレーニング」 子供時代
私が小学校5年の頃、学校の掲示板に一枚のポスターが張り出された。県が主催するキャンプの案内だった。キャンプの名前は「サバイバルトレーニング」。なんて魅力的なんだ、と思った。そして、絶対行こう、と決めた。 家に帰って両親に頼んでみると、両親は意外にもすんなり許可をくれた。 一緒に行こうと誘えるような友達が居なかった訳ではない。しかしポスターを見た瞬間から、私は一人で参加すると決めていた。学校や近所以外で、新しい友達を作りたいと考えていたのだ。 キャンプの開催地までは、電車とバスを乗り継いでいかなければならなかった。私の住んでいる町は割と都会なので、区間ごとに料金が上がって行くバスに乗るのは、初めての体験だった。両親も行ったことの無い所へ自分一人で行く、ということが私の冒険心をあおった。 キャンプ場に着くと、まず少人数の班に分けられた。男の子4人、女の子4人の計8人ずつで、6つの班があった。各班にはそれぞれ一人ずつ、大人の先生がリーダーとして担当する。以後の行動はすべて、各班で協力して行うことになった。 まず山へ行って竹を切り、それを使って箸や食器、スプーン、コップを作る。夕方になり、へとへとになった頃から料理を始める。初日の夕食はカレーだった。 カレーは私の大好物。それにお腹もぺこぺこだったので一秒でも早く作って食べたかった。猛スピードで野菜を切り終え、具を鍋の中に放り込んだ。 すると一人の女の子が、私の所にやってきてこう言った。「あのぅ。この鍋、うちの班のやねんけど…」 めちゃくちゃ急いでいたので、私は隣の班の鍋に、具を放り込んでいたのだった。ゲ! 間違えた! どうしよう!? 隣の班の女の子、怒ってるだろうな…。心配になり、おずおずと彼女の顔を見上げた。しかし次の瞬間、彼女は大きな声で 「ガハハ!」 と笑い始めた。良かった! 怒ってないし、笑ってくれた! 私はほっと胸をなでおろした。それがきっかけとなり、その子と私は仲良くなった。 それ以降、その子は私のかけがえのない親友になった。 無事夕食が終わって、キャンプファイヤーが始まった。キャンプファイヤーは班毎に行なう。せっかく仲良くなった友達は、隣の班なのが残念だった。 私達の班のリーダーは、「エゴさん」というニックネームだった。優しくて親切で良い人だった。ただ、エゴさんは年をとっていた。キャンプファイヤーの進行はリーダーによって決まる。うちの班のキャンプファイヤーは、静かにエゴさんの昔話を聞くだけという、極めて地味なものであった。 隣の友人の班はというと、リーダーは若い青年だった。リーダーはスコットランド風のスカートをはいており、友人達は何やら楽しげに踊りを習っていた。夜が更けるに連れて、R達の楽しげな笑い声と手拍子のボリュームが上がった。するとエゴさんも、負けじとボリュームを上げる。「わしの若い頃には……。」という地味なフレーズ。 エゴさんの株が上がった時もあった。例えば山へ野草を取りに行った時などは、エゴさんがリーダーで良かったと思った。エゴさんは食べられる野菜に詳しかったので、うちの班は食べるものが豊富に取れたのだ。 何しろ、キャンプのタイトルが「サバイバルトレーニング」である以上、自分の食べるものは自分で取る、という趣旨なのである。子供たちは皆、常にお腹を空かせている状態だった。 「鮎のつかみどり」というのがあった。取った鮎がその日の夕食になるのだ。「取れなかったら夕食抜き」とリーダーに脅されていたので、みんな死に物狂いで掴んだものだ。そんな苦労をしてとった鮎だから、格別に美味しかった。 最後の夜は、みんなそろって盛大なキャンプファイヤーをすることになった。私はそれを心待ちにしていた。あの楽しそうなダンスを、教えてもらえるかもしれない。私はあまりにも興奮していたようである。肝心のキャンプファイヤー直前に鼻血が出てしまい、医務室で過ごす羽目になったのだ。 医務室の先生がこう言った。「鼻血が止まったら、キャンプファイヤー場に行ってみなさい。みんなにおにぎり2個ずつとお味噌汁を配っているはずよ。」 くどいようだが、このキャンプの名前は「サバイバルトレーニング」。言い換えれば空腹に耐える我慢大会のようなもの。ずっと空腹状態が続いているのだ。「おにぎりが食べられる」というのは、予想外のグッドニュースだった。 鼻血を止める方法は知っていた。鼻をかんで血を出し切ってしまうのだ。そうやって、私はすばやく鼻血を出し切り、キャンプファイヤー場へと急いだ。 ようやく着いた頃には、火も小さくなっていて、食事も終わった後だった。 「私のおにぎりと味噌汁はどこ??」 同じ班の子に聞いてみた。するとその子は申し訳無さそうにこう言った。「つい今さっき、モモコちゃんがあなたの分も食べちゃったわよ。」 目の前が真っ白になった。あまりにもショックだったので、モモコちゃんを怒鳴るとかそういうことは、何も思いつかなかった。ただ、力なく地面に座り込んだ。 モモコちゃんというのは私の班にいた、ちょっぴり太目の女の子だった。それ以来私が、「モモコ」という名前に敏感に反応してしまうようになったのは言うまでもない。
「ラボパーティ」子供時代
私がまだ4歳の時、母は私と兄の為に「ラボパーティ」というものを見付けてきた。「ラボパーティ」というのは子供の英語教室みたいなもの。英語劇をしたり、英語の歌を習ったりしながら英語に慣れていくのだ。4-5年しか所属しなかったが、まだ幼い頃に英語に触れる機会が持てて良かったと思う。 ここでの体験は英語だけに留まらない。発表会やクリスマスパーティなどのイベントでは、たくさんの人の前で話す訓練になる。所属している子供の年齢は園児から高校生までと幅広いので、大きいお兄ちゃんお姉ちゃんの友達が出来る。高校生になると、アメリカで一ヶ月ほどホームステイプログラムに参加する。私達チビッコ組は大きいお兄ちゃんお姉ちゃん達の冒険談を、ワクワクして聞き入っていたものだった。 私達チビッコ組はアメリカホームステイの準備段階として、日本国内でのホームステイプログラムに参加する。私は名古屋までホームステイに行った事があるし、逆に私の家族がホストファミリーとして子供を受け入れたこともあった。ラボパーティでの経験は全て、私という人格を築き上げる為の貴重な材料になった。 大人になってからも、母とラボパーティの先生は連絡を取り合っていた。 ラボパーティで先生をしていた方はアメリカ人と再婚して、オレゴン州ポートランドに住んでいた。ひょんなことからその先生に会いに行くことになった。 先生には娘さんがいた。私より2歳年下で、当時サンフランシスコの大学院生だった。私はロサンゼルスからサンフランシスコまで飛行機で行き、彼女と落ち合った。彼女と再会するのは、実に25年振り。 私たちはサンフランシスコでレンタカーを借りて、先生の住むポートランドを目指した。 先生の家で一週間ほど過ごした後、私と友人はまたサンフランシスコに戻った。 25年振りの再会が、まさかアメリカという土地で果たされるとは思っていなかった。これからもこんな風に意外な出来事が舞い込んでくるのかな。そう考えると、人生って面白いなぁと思う。
「兄」子供時代
私には一つ年上の兄がいる。 幼い頃、兄は近所でちょっとした有名人だった。肌は白く、長い上向きまつ毛と丸くて大きな目をしていた。 一見女の子に見えるくらい、かわいい顔をしていたのだ。 「将来はアイドル歌手になるかも」大人達はそんな風に言っていた。 一方私はというと、どちらかといえばブサイクだった。まつげは下向きで、目は細くて垂れていた。 誕生時のサイズは兄よりも私の方が随分大きく、頭も大きかったので、よく壁や柱に激突していた。 だから、顔に生傷が絶えない子供だった。 兄と私はよく二人で散歩に出掛けた。最後には決まって迷子になり、見知らぬ大人達に助けてもらって家に帰ってくるのだった。 「君はお兄ちゃんなんだから、妹をしっかり守ってあげるんだよ」 そう言って大人達は私の肩をポンと叩く。私のことをお兄ちゃん、兄のことを妹だと勘違いしていたようである。そういうことが何度かあったので、幼心にも 「私が兄を守らなければいけないのだ」 と思っていた。 兄が5歳、私が4歳の時、ちょっとした事件が起きた。兄が近所の悪ガキに追いかけられて腕の骨を折ったのだ。私はとても怒っていた。仕返しに行こうと思った。重い野球バットを引きずって玄関の所まで歩いていった。ドアノブに手が届かずもたついている所を母に見付かってしまい、私の「お礼参り」は果たせなかった。幼い私はただひたすらに、兄を守ろうと考えていたのである。
「ユニーク」子供時代
私はとても変わった子供だった。感受性がとても豊かだったのだ。豊か過ぎたと言っても良い。人の感情がはっきりと色で「視えて」いた。 悲しんでいる人のそばにいくと自分も悲しくなって泣いた。怒っている人のそばでは一緒に怒った。嬉しそうな人のそばだと自分も嬉しくなる。そんな風に、他人の感情に巻き込まれるのは嫌だった。しかし自分でコントロールする術を知らなかった。 私の子供時代を表現する言葉は「ユニーク」という一語に尽きる。この言葉は、学校の先生が書く、通信簿の備考欄に必ず登場していた。 「ユニーク」 と表現されることがすごく嫌で、通信簿を受け取るときにはいつも、「今回はユニークって書かれていませんように」 と祈るのだが、その祈りは聞き入れてもらえてなかった。 感情をコントロール出来ないという以外にも、私の思考回路はみんなとは違っていた。 5歳くらいまでは、過去生の記憶がまだ鮮明に残っていた。夢として現れることもあったし、起きている時間に意識が異次元に飛ぶこともあった。 その頃は、誰にでも過去生の記憶が残っているのだと思っていた。だから平気で母や友人に話した。すると皆は決まって私のことを変人扱いした。そしてやっと分かった。誰にでも見えたり感じたりするものではないのだと。 とりわけ母はそういった霊的な話を嫌った。私が話し始めると、私の言葉をさえぎったものだった。今でも母は、スピリットの話や過去生の話、スピリットワールドの話といったものをひどく嫌っている。 私が自分の過去生に関係あるだろうと感じていたのは、アメリカインディアンのナバホ族とアパッチ族、それにラコタ族。 誰に教えてもらった訳でも無いのに、記憶に残っていた。 ナバホの大地に初めて行った時、懐かしさで涙が込み上げてきた。私のスピリットは、この土地とこの人々のことを覚えていた。 ナバホに通い始めて11年目になる。私が懐かしいと感じているのは、ナバホの人達の宗教観なのかもしれない。 子供の頃、話してはいけないと言われ続けた話を、この地では普通に話すことが出来る。 それによって私のスピリットが癒されているのだと思う。