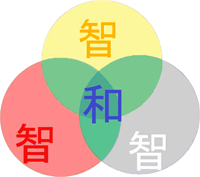-
「修羅場」ナバホ体験記
彼らの敷地に入った瞬間、ぞっとするほどの嫌な空気を肌で感じて鳥肌が立った。
私が暮らしていたトレーラーハウスに入ると、私のベッドの上に彼が腰掛いていた。 彼の隣には、機関銃の手入れをしている別の大男がいる。
??? どういうこと???
トレーラーハウスには鍵があって、鍵は一つしかないと聞かされていた。 つまり、私しか持っていないはずだった。
彼らは合鍵を持っていたんだ。 私には一つしかないと嘘をついていた・・・。
私は無理やり笑顔を作って、男性に 「元気?」 と挨拶をした。
彼も 「やぁ」 と返事をした。 彼もまた、作り笑いを浮かべた。
彼は大男の事を、自分の従兄弟だと紹介した。 従兄弟は、私と握手をしようとせず、私の挨拶に対する返答もせず、ただ黙々と機関銃をクロスで磨いている。
私の両手と両足がかすかに震え始めた。 それを気付かれまいと必死に平静をつくろいながら、私は荷物をまとめはじめた。
「何してるんだ?」 男性がすかさず大声で私に聞いた。
「ナバホの両親の家に引っ越そうと思って…。今までありがとうね」
そう返答すると、彼の表情がさっと青ざめた。 彼は従兄弟に目で合図をし、従兄弟はさっとトレーラーハウスの外に出ていった。 部屋の中には私と彼だけが残された。
彼はすごい勢いで私の体を引き寄せ、「君を愛している。出て行かないでくれ。ずっと俺とここにいてくれ。 1人ぼっちにしないでくれ」 と懇願した。
びっくりして突き放そうとしたが、彼の力が強すぎて身動きができない。
「何言ってるの? あなたには奥さんがいるじゃない? あなたは1人じゃない」
「俺の事を好きだって言ったじゃないか?」と彼が続ける。
・・・確かに私はそう言った。 それは覚えている。 何日か前に彼が ”Do you like me?” と聞いたとき、軽く”Yeah” と答えた。
でも私は ”I love you.” と言った訳ではない。 私の中では、 ”like” と ”love” は全く別物だった。 だから友人として ”like” を使っても罪ではないと勝手に解釈していた。 それに、友人同士でも親しければ ”I love you” ってみんな簡単に言うし・・・。
「俺の事を好きだと言ってくれたのに……。 君も俺を裏切るのか? 君も俺を捨てるのか? 許さない。 君を絶対に放すつもりはない。 ここから出て行くことは絶対に許さない」
泣き落としでは駄目だと感じたのか、彼は従兄弟を家の中に呼んだ。 彼の従兄弟は大柄な男で、 身長は180センチを軽く超えている。 しかも銃を持っている。 ・・・冗談でしょ?・・・ しかし、従兄弟は全然笑顔じゃない・・・。
もう駄目だと思った。 こんな所で殺されてしまうんだろうか? 体がガタガタと震えた。 涙と鼻水まみれで、本当に惨めな姿だった。
そのとき、トレーラーハウスの外で、車のドアが開く音がした。 一緒に住んでいたナバホ女が帰ってきたのだ。 平日の昼間に、彼女が帰ってくるなんてことは今までなかった。
彼女は私の名前を呼んだ。 優しく呼んだという訳ではなく、切羽詰った声で叫んだ。
私が彼女の家に入ろうとすると、彼も私の後ろから付いて来て一緒に入ろうとした。 それを彼女が制した。
「私はこの子に用事があるの。 あんたは外で待っていなさい」
彼女にぴしゃりと言われて、彼は怖気づいた子犬のように後ずさった。
「さてと……。何があったのかを話してごらんよ」
彼女はそう切り出した。
どうして彼女が平日のこの時間に家に戻ってきたのか理由を知りたかったのだが、聞かない方が良いような気がした。
私は、「ナバホ両親の家に引っ越すことにした」 とだけ彼女に言った。
「どうしてなの? もっと話すことがあるでしょ? 全部話してよ」 と彼女は執拗に問い続けたが、私はそれ以上何も言わなかった。
彼女は大きなため息をついてから、こう言った。
「彼はあなたを愛してるって私に言ったのよ。 あなたと結婚するつもりだと。 あなたもそれに同意したともね」
どうしてそんな話になってるの?
「そんなこと言ってない!」私はそう反論した。「友人として好きだとは言ったけど、愛しているとは言ってない! 結婚するなんて言ってない!」
「同じ事よ」 と彼女が私を制した。
「あなたが彼を炊き付けたことには変わりは無い。 彼は精神的に病んでいる。 私は彼から離れたいとずっと願ってきた。 彼の世話をするのがもう嫌になった。 だからあなたに彼を引き取ってもらいたいと思ってる」
-
「親はいつだって親」ナバホ体験記
マークと約束をしたので、ナバホ両親の家に会いにいった。
私はナバホ両親の助言を聞き入れずに勝手な行動をしていたので、ナバホ両親の家に行くのは勇気が必要だった。マークがあんな風に私を駆り立ててくれなかったら、きっと来られなかったと思う。
私の心配をよそに、ナバホ両親はいつものように暖かかった。 家の前で車を降りた瞬間に、ナバホ父は私をきつく抱きしめてくれた。
「俺達のワンパク娘は元気にしていたか?」
”naughty daughter”(ワンパク娘) と呼ばれてムッとしたが、確かにそうだ。 私は両親の言いつけを聞かない強情な娘だった。 両親は私が彼らと暮らす事を最初から反対していたのだから・・・。
「君は誰の事でも簡単に信用しすぎる。 もっと注意を向けなさい。 もっと気を付けなさい」
彼らにこの言葉を何度言われたことか……。 それでも私は両親の言いつけを聞かず、家を飛び出して行ったのだ。
マークに話したのと同じことをナバホ両親に話した。 ナバホ父はこう言った。
「今からすぐに彼らの家に戻って、荷物を全部取ってきなさい。 彼らには何も言う必要はない。 両親の所に引っ越すんだとだけ言いなさい。 君がどんな弁明をしたところで、彼らには通じないだろう。 彼らは君にウィッチクラフトをかけてくるかもしれない。 いや、もうかけているんだろうな。 家に戻ってきたら、しばらく君は外出禁止だ」
両親はそのまま私と一緒に、彼らの家の前までついてきてくれた。
彼らの敷地の前で、私は車を降りた。
母は私のことをとても心配していて、「この子1人じゃ危ないから一緒に行こう」 と父に言ってくれたが、父が母を制した。 そして父は、私の目を見て、こう言った。
「ここから先は、君1人で行きなさい。 君はここから修羅場をくぐり抜けてこなければならない。 君なら乗り越えられる。 俺は君の強さを信じている。 彼らは君を引き止めるために、いろいろ言ってくるだろうが、何を言われても何をされても、必ず俺達の家に戻って来い。 絶対忘れるな。 俺達が君の両親だ。 君には俺達がついている。 君は1人ぼっちではないんだ」
寒気がした。
これから何が起こるっていうんだろう? 修羅場? まさか? 怖いけど、自分で蒔いた種なんだ。 自分で決着をつけなきゃ・・・。
-
「ナバホ女性の嫉妬」ナバホ体験記
住み始めてずっと親切にしてくれていたナバホ女性が、ある時を境に私に冷たく接するようになった。原因が分からなかった。
その頃になると、彼らの敷地で一日中を過ごすのが嫌で、私は何かと理由をつけて外に出掛けるようになっていた。
その日は友人のマークの家に行った。事情を話してみると、彼は真顔で私にこう聞いた。
「その女性が君の事をうとましく思っている原因を、君は本当に分からないの?」
分からなかった。私はその男性にも女性にも、出来る限りの誠意を尽くしているつもりだった。
マークは思いがけないことを言った。
「その女性は君に嫉妬しているんだよ。 君が彼のことを奪ってしまうのではないかと恐れているんだ。 君はその男のことを好きなの?」
嫉妬? まさかね。 そんなはずは無いと思った。
私はその男性のことを友人として好きだし、そもそも彼の面倒を見てやってくれと頼んだのは彼女だった。
「彼は車の運転が出来ない。 だからどこか用事があるときには一緒に行ってあげて欲しい。 本当は自分がそうしなければいけないのだけど、自分には仕事があるので毎日そばについている訳にはいかない。 あなたが彼のそばにいてくれると助かるのよ」
だから私は、この男性のそばにいることが彼らの敷地にいさせてもらえる条件だと思っていた。
大体、私は、誰かから嫉妬されるなんて、今まで経験したことが無かった。 私に頼んでおきながら、嫉妬するなんて、矛盾している。 だから彼女が嫉妬しているなんて、あり得ないと思った。
マークはこう続けた。
「君はナバホの性格をもっと知らなきゃ。 ナバホの人達はとても嫉妬深いんだ。 勿論、全員じゃない。 良識のあるナバホだってたくさんいる。 でも、ナバホの人達の中で嫉妬深い人はすごく多い。 これが事実だ。 君はウィッチクラフトという言葉を聞いた事があるか?」
またこの言葉だ・・・。 「ある」と私は答えた。
マークはこう聞いた。
「俺はその男のことを知ってると思う。 そいつは以前、ミュージアムで働いてたことことがあるか?」
そう言えば彼からそんなことを聞いたことがある。
「そうだよ」と私が答えると、マークの表情は険しくなった。
「そうか・・・。 だったら君は、一刻も早くそこを出なきゃいけない。 君はもう彼らにウィッチクラフトをかけられているかもしれない。 捕らわれてしまっているんだ。 俺に分かるのは、君がそこに居続ければ、どんどん危険な状態になるということだ。 君はナバホの両親に相談しなきゃいけない。 君の両親は立派な人達だ。 きっと君を助けてくれる」
助けてくれるってどういうこと? そんなに危険な人達なの? 両親に助けてもらわないといけないくらい、私は危険な状態にあるの??
心臓がバクバクした。
マークはその日、「ナバホの両親に会いに行くこと」 と 「彼らの敷地から一刻も早く出ること」 を私に約束させた。