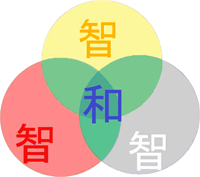This year 2016 is my 8th year to live in America, and I have stayed at the same area for these 8 years. My first friend on this area is a Honduras woman. She is 19 years younger than I am. It is a huge gap in physical age, but from the perspective of spirits, the person’s spiritual age matters, rather than physical age. Before I make my friends, I see through their eyes in order to find out their spiritual age. When I met her for the first time, I instantly noticed that she is an old age in spirituality. She is quiet, patient, and kind to people, and I really like her humble attitude to people.
In this 8 years, we had shared lots of precious experiences. When I got pregnant, she arranged a baby shower for me and my baby-to-be-born. She introduced me to her close friends. Whenever I got hurt mentally, I would visit her and chart with her. She was like a grandmother to me. She would listen to me carefully, never cutting me off during I was talking. Then, after I finished talking, she would give me encouragements or appropriate advice. She is also an immigrant from a foreign country so that she had gone through tough days in communicating in English as well as prejudices as a minority. That is why she exactly knew how I felt those days.
In these recent years, her husband had started talking about moving to another state. I thought it would never happen, because simply it never happened for them to move.
However, the movement happened all of a sudden.
One day, all of a sudden, her husband decided to move, and took necessary actions right away, and moved to another state. They moved even before they rented or bought a house there.
Right before she moved, I went to see her and we hugged each other at the last moment. We could not stop our tears falling down, lots of lots of tears. We cried and cried, because we both somewhat sensed that this would be truly the last for us to see each other on this life. We both felt something had finished. When I was hugging her, shedding tears, my family souls whispered to me “graduation ceremony from this land”.
I think she came into my life as a guardian angelic figure to support me so that I could fit myself in this land, America. I probably had helped her in some way, too. Then, when our timing matched; I am ready to move to another land, and she is ready for her new adventure at her new land, our farewell happened.
When you think back your life, you also will notice a guardian angelic person came into your life, and after you had achieved something, the person naturally disappeared from you. I think this is how we support and interfere with one another. Isn’t is miraculous and wonderful? Let’s enjoy and cherish every new encounter in our life, because no exactly same situation will come back to us again.